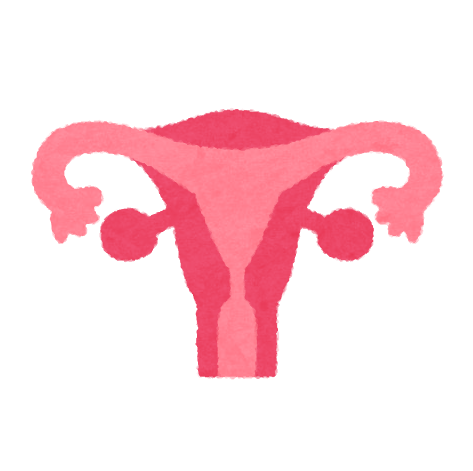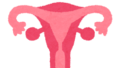女性ホルモンは働き者
更年期におけるホルモン変化は、体のあちこちに“連鎖的な影響”を及ぼします。
特に影響が大きいのは 女性ホルモンと呼ばれているエストロゲン と プロゲステロン の減少です。
まずは、女性ホルモンがどんな働きをしているのかについて取り上げます。
エストロゲン
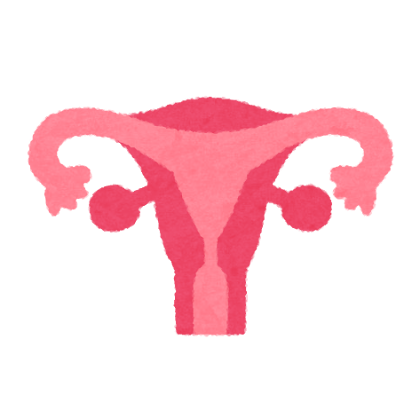
エストロゲンの主な働き
生殖器の発達と維持
エストロゲンは、女性の生殖器、すなわち子宮、卵巣、膣、乳腺の発達を促します。思春期にはエストロゲンの分泌が増加し、これらの臓器が成熟して妊娠・出産が可能な状態になります。また、エストロゲンは膣の粘膜を保護し、潤いを保つ働きも持っています。
第二次性徴の促進
月経周期の調節
エストロゲンは、プロゲステロンとともに月経周期をコントロールします。卵胞刺激ホルモン(FSH)によって卵胞が成長し、エストロゲンが分泌されると、子宮内膜が厚くなって受精卵を迎える準備が整います。排卵後はエストロゲンの値が下がり、プロゲステロンが優位となりますが、妊娠しなかった場合は両者が減少して月経が始まります。
骨や関節の健康維持
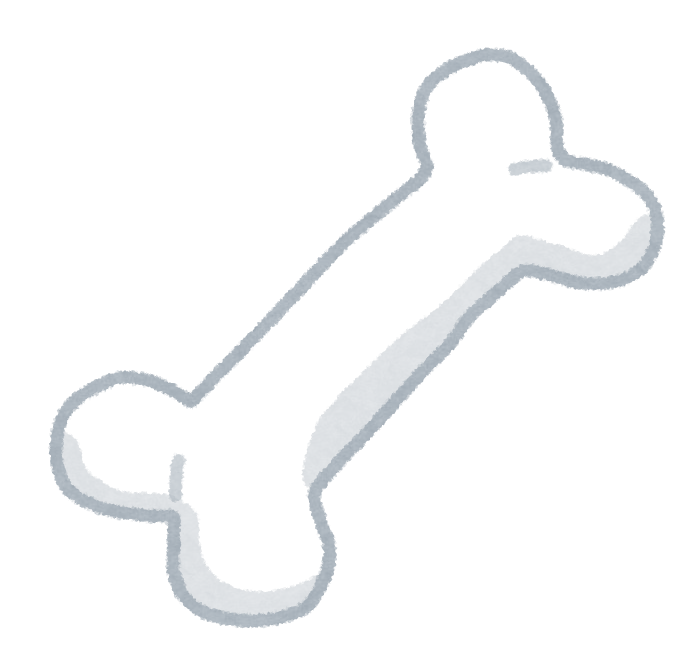
エストロゲンは骨量の維持にも不可欠です。骨形成を促進し、骨吸収を抑制することで骨密度を保ちます。閉経後、エストロゲンの減少によって骨粗しょう症のリスクが高まるのはこのためです。
関節、腱・靱帯を守る働きも持っています。
脂質代謝の調整
エストロゲンは血中コレステロールのバランスを調節し、善玉コレステロール(HDL)を増やし、悪玉コレステロール(LDL)を減少させます。これにより動脈硬化や心疾患のリスクを低減します。
心血管系の保護
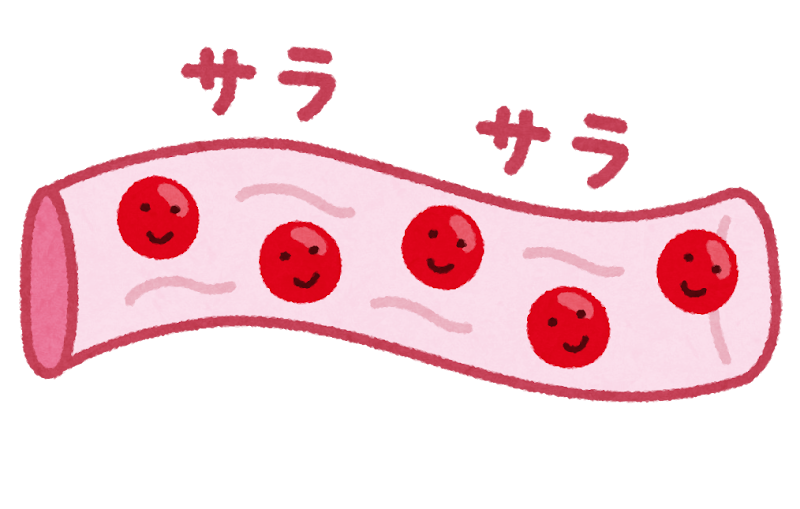
エストロゲンによる脂質代謝の調整や血管拡張作用は、心血管系の健康を守るうえで重要です。女性が閉経後に心疾患のリスクが高まるのは、エストロゲンの減少が関与しています。
皮膚や髪の健康
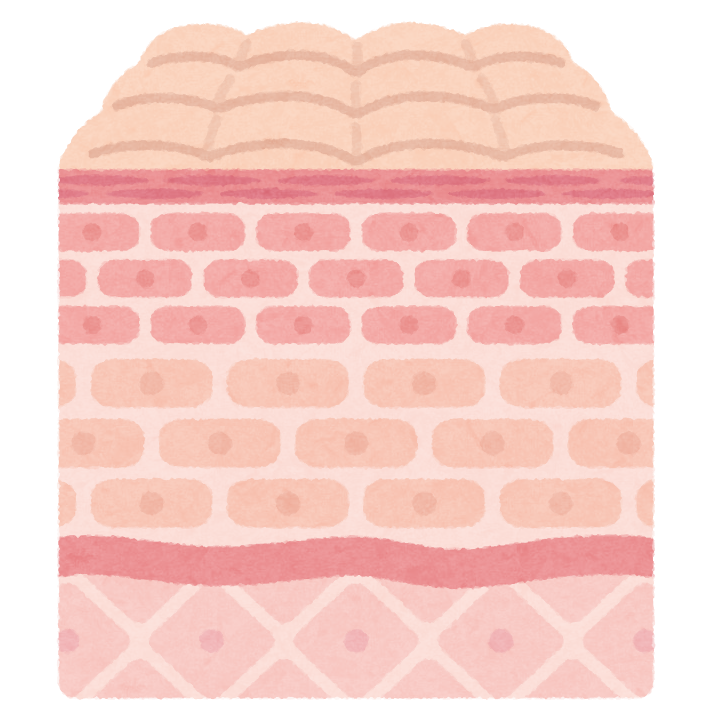
エストロゲンは皮膚のコラーゲン生成を促し、ハリやみずみずしさを保つ働きがあります。また、髪の成長を助け、抜け毛を抑える効果も報告されています。
脳や感情への影響
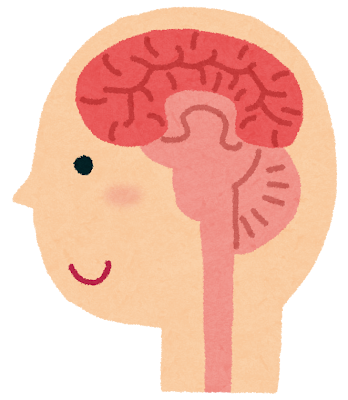
エストロゲンは脳内の神経伝達物質のバランスにも関与し、記憶力や気分の安定に寄与します。閉経期や月経周期の変動による気分の変化には、エストロゲンの作用が深く関わっています。
エストロゲンの減少による影響
血管・自律神経への影響

- のぼせ・ほてり(ホットフラッシュ)
- 発汗、動悸、寒気
エストロゲンは血管の収縮・拡張を安定させ、自律神経を整える働きがあります。
そのサポートが弱まると、血流調節が乱れます。 - 自律神経の乱れは、膀胱の収縮や尿意のコントロールに影響し、残尿や頻尿が増える。
残尿があると、細菌が繁殖しやすくなる。
骨や関節への影響
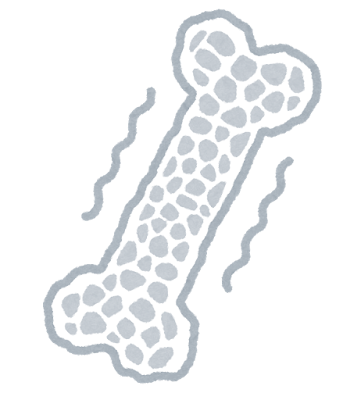
- 骨密度の低下(骨粗しょう症のリスク増加)
エストロゲンは骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑えるため、減少すると骨がもろくなります。 - エストロゲンが減ると関節の潤滑液が減り 摩擦が増え、軟骨の代謝も低下
- 靱帯や腱が硬くなり、その結果、指のこわばり・痛み・腫れが出やすくなります。
皮膚・粘膜への影響

- 肌のハリ低下、しわ・たるみ
- 膣の乾燥(性交痛や感染リスク)
コラーゲンや水分保持を助ける働きが弱まります。 - 膀胱や尿道に細菌が侵入しやすくなる(膀胱炎などのリスク)
脳・感情への影響

- イライラ、気分の落ち込み、不安感
脳内のセロトニン・ドーパミンなど、感情に関わる神経伝達物質の働きに影響します。
プロゲステロン
プロゲステロンの主な働き
妊娠準備・維持
- 子宮内膜をふかふかにする
排卵後、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くし、栄養豊富な状態にします。 - 子宮の収縮を抑える
着床した受精卵が安定して育つようにサポートします。
月経周期の調整
- 排卵後の高温期をつくる(体温を0.3〜0.5℃上げる)
- プロゲステロンが減少すると子宮内膜が剥がれ落ち、月経が始まります。
中枢神経系への作用
- 鎮静・安眠作用
GABA(抑制性神経伝達物質)の働きを促進し、心を落ち着かせます。 - ストレス耐性の向上
体液・代謝への作用
- 体内のナトリウムや水分バランスを調整
- 一時的に水分を保持しやすくする(むくみの原因にもなる)
乳腺への作用
- エストロゲンと協力して乳腺を発達させる
- 妊娠時には母乳の準備を促進
プロゲステロンの減少による影響
- エストロゲンより先にプロゲステロンが減少します。
- 40代半ばになると排卵の回数が減り、排卵がない周期(無排卵周期)が増えるため、プロゲステロン分泌も減少。
- このため、更年期初期にはエストロゲンはまだあるのにプロゲステロン不足の状態になりやすく、ホルモンバランスが崩れます。
睡眠への影響
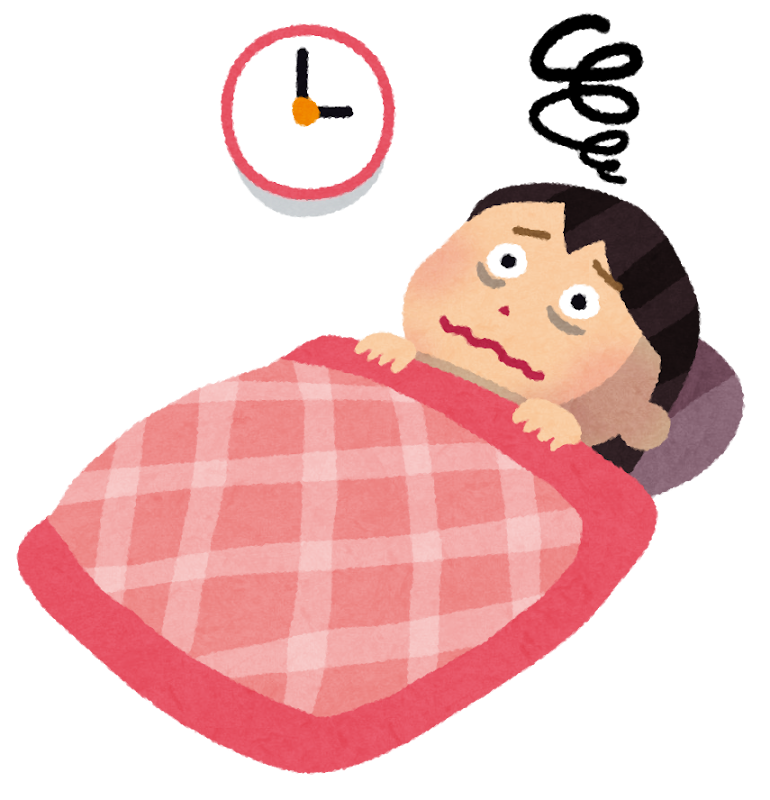
- 眠りが浅くなる、中途覚醒が増える
プロゲステロンは脳に落ち着きを与える作用(GABA促進)を持ちます。
むくみや体重変化

- 水分保持の調整が乱れ、むくみやすくなる
- 代謝の低下で体重増加しやすい
月経の乱れ
- 月経周期の短縮や経血量の変動
排卵が減少し、プロゲステロン分泌が不安定になるため。
エストロゲンとプロゲステロンの“バランスの崩れ”の影響
更年期初期はエストロゲンよりも先にプロゲステロンが減るため、
一時的に「エストロゲンドミナンス(エストロゲン過剰相対状態)」が起きることがあります。
このときの主な症状として
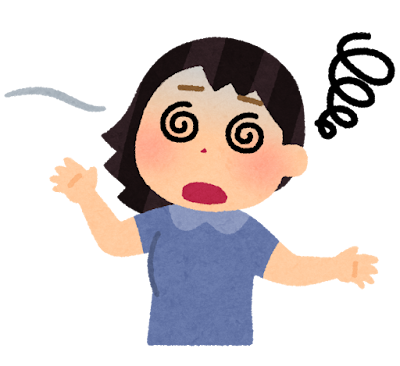
- 乳房の張りや痛み
- PMS(イライラ、気分変動)の悪化
- 頭痛、めまい
などが現れます。
ホルモンバランスが変化する流れ
更年期前期
プロゲステロンが先に減少 → 情緒不安定や睡眠の質が低下する
閉経前後
エストロゲンが急激に減少 → 血管、自律神経、骨、皮膚、脳への影響が顕著に現れる
プロゲステロン・エストロゲン両方減少
慢性的な倦怠感、体型変化、老化の加速感
驚きませんか!?
女性ホルモンは健気にも、こんなにたくさんのことをしてくれていました。
残念なことに、このことに気づくのは多くの場合
更年期で色々な症状が出てきた時です。
「こんなにも色々な事をしてくれていたのね」と
失って初めてその大切さに気付かされます(T^T)
これからは
女性ホルモンがやってくれていたことを
自分で努力をしないと今までの様にはいかなくなります。
逆に言えば
生活習慣や食生活など見直す良いきっかけでもあります。
できる事から始めてみませんか?
<更年期のおはなし関連記事>
*吉祥寺駅徒歩3分 女性専用鍼灸 みうら堂はり灸院*